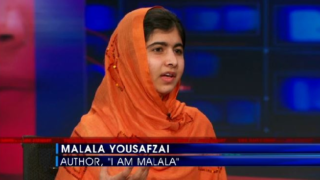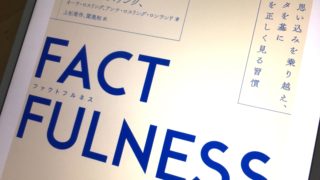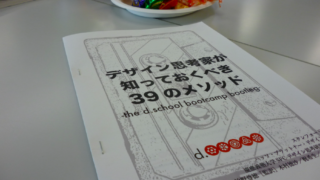日本では参議院選挙、アメリカでは大統領選挙、イギリスではEU離脱の国民投票、アジアでも台湾総統選やフィリピン大統領選等があり、今年は大きな選挙が多いなぁという印象です。
4年前にサンフランシスコに住んでいた時、オバマの二期目の大統領選があり、アメリカではビジネスの領域で活躍しているマーケターやエンジニアたちが、そのスキルを活かして選挙の陣営に参加する状況があると知りました。
大統領選ではネットの活用も盛んで、「米国の大統領選におけるネット活用はマーケティング業界のF1レースとも言われ、グローバル企業ですらそこから学びを得るほど」という話も。
参考:米仏大統領選のネット活用の実態、勝敗を分けたのは人材と資金力
http://business.nikkeibp.co.jp/article/nmgp/20130313/244968/
日本ではそういった状況にはなっていないのかもしれませんが、このアメリカ滞在がきっかけで、政治とマーケティング・PRに関連する本を読むようになりました。その中から特に勉強になったものをいくつか紹介したいと思います。
(随時更新予定)
この記事を書いた当初、実は衆議院議員の広報・コミュニケーション担当秘書をしていました。日本には政治×マーケティング分野の先行事例が少ないので、よく本を読んで参考にしていました。
もくじ
戦争広告代理店〜情報操作とボスニア紛争
国際政治におけるPR情報戦を描いたノンフィクション。ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争時、アメリカにあるPR会社がボスニアをクライアントとして暗躍し、巧みに国際世論をつくり、西側先進国の支援を得て紛争に勝利する過程を描いています。
小説のように手に汗握る展開で引きこまれました。「空気」はどう作られていくのかを知るために読んでおきたい名著です。
作中、筆者の高木さんが日本のPR戦略について書かれている部分があったので引用します。
日本の外交当局のPRセンスはきわめて低いレベルにある。これは構造的な問題である。アメリカの高級官僚は、民間で活躍してから役所に入る、あるいは官僚となってからも、いったん外に出て経験を積む人が多い。彼らの能力はそういう民間の、食うか食われるかの厳しい世界の中で磨かれるのだ。
(中略)
日本のように大学を卒業してすぐに外務省に入り、一生その中で生きていく外交官が大半、というやり方では永遠に日本の国際的なイメージは高まらないだろう。
本書が出版されてから15年程経ちますが、この状況はあまり変わってなさそうですね。
「戦争広告代理店」は15年ほど前の本ですが、比較的最近になってからこの本の著者の高木さんが同じテーマで書かれた以下の本もおすすめです。アルカイダの情報戦術や日本の五輪招致等が取り上げられています。
国際メディア情報戦
「オバマ」のつくり方 怪物・ソーシャルメディアが世界を変える
前回のブログ:オバマ大統領の選挙戦を追ったドキュメンタリー「バラク・オバマ 大統領への軌跡」 でも紹介しましたが、オバマ大統領の選挙のオンラインの広報戦略について、実際にオバマの選挙陣営のスタッフをしていたラハフ・ハーフーシュが解説しているこの本も面白かったです。
2008年の選挙なので少し古いところもありますが、今でも十分に通用する内容だと思います。
また、アメリカ在住のマーケターである大柴ひさみさんが、2年間に渡りオバマのキャンペーンを追いかけてブログを書かれていたのですが、その時の内容をまとめた以下の本も、キャンペーンの詳細と分析が分かると同時に、当時の選挙戦の熱狂を感じられる良書でした。
YouTube 時代の大統領選挙 (米国在住マーケターが見た、700日のオバマキャンペーン・ドキュメント)
オバマの2期目の選挙(2012年)については、この記事で読んだITチームの豪華さに驚きました。日本の選挙でこんなチームが作られるのは何年後でしょうか…
参考:オバマ大統領の再選を勝ち取ったITチームは、どんなメンバーで構成されていたのか?
http://www.publickey1.jp/blog/12/it_2013.html
こちらの記事では、2012年のオバマの選挙でのアプリやソーシャルメディアの活用について紹介されています。4万人のボランティアの活動をサポートするアプリが200種類あったとか、なんだか想像できない規模ですね。。
参考:ビッグデータはいかにオバマを勝利させたか?
http://tsuda.ru/tsudamag/2013/05/2639/
マーケティング・デモクラシー: 世論と向き合う現代米国政治の戦略技術
政治マーケティングについて、理論から具体的な方法まで400ページ以上に渡って分析・解説した本。クリントン、ブッシュ、オバマが大統領選挙、また政権運営でどんなマーケティング戦略をとっていたかについても掘り下げています。
日本の政治マーケティングの現状についても最後に少し取り上げられていました。
以下はこの著者の方のインタビュー記事。長文で読み応えのある記事です。これを読んでピンときた方は本の方もぜひ。
参考:何に使うか、目的意識がはっきりしなければビッグデータは意味がない。オバマの選挙からそれが見えてくる ―『Journalism』7月号から―
http://webronza.asahi.com/journalism/articles/2014071500001.html
また以下は、特にホワイトハウスの情報発信について解説した本です。上記の本と同じくクリントン、ブッシュ、オバマの3人の大統領が、どんな意向で、どんなチームをつくり、どういう情報発信を行っていたが詳しく書かれています。
チームの組織図も載っていて、「大統領夫人スピーチライター」なんて役割の人もいました。
ホワイトハウスの広報戦略―大統領のメッセージを国民に伝えるために
権力奪取とPR戦争
日本の政治分野のPRについては、この本が現場の具体的なエピソードが分かっておもしろかったです。
政党のキャッチコピーが決まるまでに、どの議員が関わってどういうプロセスで進められたのか、また電通やフライシュマン・ヒラード等の広告代理店・PR会社がどう関わっていたか等、日本の政治のPRの裏舞台が垣間見える内容でした。
たとえば、小泉純一郎総理時代の自民党の「改革を止めるな」という有名なキャッチコピー。当初、電通から提案したのは「改革を止めるな」と「改革は国民との約束だ」の2案でした。
小泉総理が選んだのは「改革を止めるな」でしたが、当時自民党のPRを手がけていたプラップジャパンは、「PR業界の常識では、否定形のスローガンは見ている人の心に響きにくい」という理由で反対します。しかし小泉総理は「『改革を止めるな』でいく」、ということで意見を曲げなかったそうです。
政党や議員がクライアントになりそうなビジネスパーソン(あまりいないと思いますが…)は事前に一読しておくと、業界の雰囲気がつかめるかもしれません。
日本政治とメディア – テレビの登場からネット時代まで
こちらは戦後、政治家とメディアの関係がどう変化していったかの全体像が分かる一冊です。新聞、ラジオ、テレビ、インターネット等、新しく登場したメディアをうまく活用しようと試行錯誤する政治家たちと国民のコミュニケーションの変遷がまとまっています。
その時代の政局の解説も挟まれているため、政治にあまり詳しくない方でも読みやすく感じると思います。
日本人はなぜ戦争へと向かったのか: メディアと民衆・指導者編
NHKスペシャルで2011年に放送された「日本人はなぜ戦争へと向かったのか」というシリーズの書籍版です。軍とメディアが国民の戦意を高揚するために築いた共犯関係を、当時の新聞記者等の証言を交えながら検証しています。
またあの時のような道に進まないよう、民衆の「熱狂」がどう作られるかについて知っておきたいですね。
(本書の後半は当時のリーダー達の迷走が書かれています)
マーケティング化する民主主義
情報社会学者の西田亮介さんが、最近の日本政治のマーケティング戦略について分析した一冊。18歳選挙権やSEALDs等、最近のテーマも取り上げられています。
また、現実味を帯びてきた憲法改正の国民投票についても分析されています。現役の国会議員(平将明議員、小林史明議員)との対談もあり、具体的なエピソードも多く、分かりやすかったです。
情報参謀
自民党が野党に転落した直後から与党に返り咲くまでの期間、テレビやネットのデータ分析やPR戦略を担当した小口さんがその4年間を総括した一冊。日本の政治における情報戦の最先端が分かって勉強になりました。
以前クローズアップ現代で自民党のネット選挙チーム「T2」が紹介された時があったのですが、本書を読むと、小口さんの活動が発展したものがこのT2だということが分かります。
検証“ネット選挙” – NHK クローズアップ現代+
http://www.nhk.or.jp/gendai/articles/3383/1.html
ソーシャルメディアやスマートフォンの普及により、今までは情報の受け手としての立場がメインだった私たちも、どんどん情報を発する立場になってきています。日々受け取る情報をしっかりと吟味し、安易に流されないようにするために、こういった本を読む価値は大きいと思っています。
今回の内容と近いテーマの記事
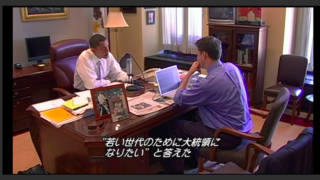



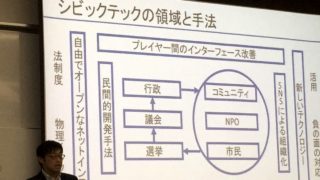

















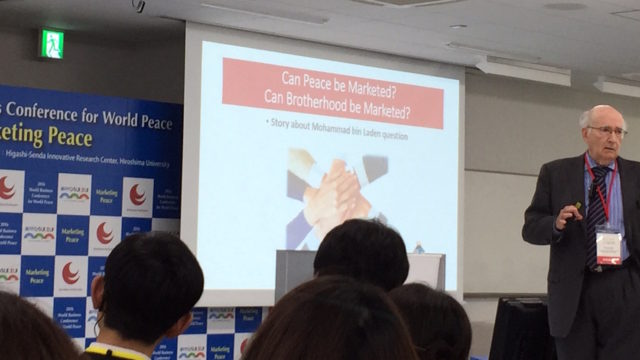


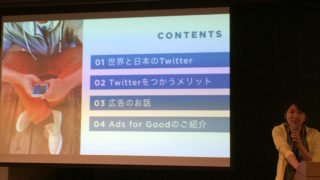

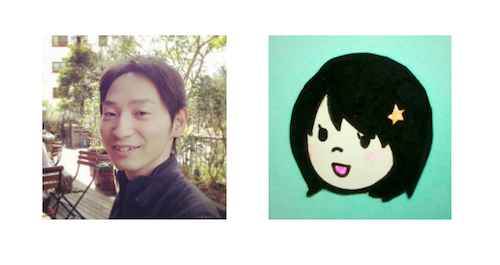 子育て、夫婦、働き方、政治、行政、NPO、マーケティングなどのテーマを通して、これからの社会の変化を考えるメディアです。加藤たけし&佐藤茜が夫婦2人で運営しています。
子育て、夫婦、働き方、政治、行政、NPO、マーケティングなどのテーマを通して、これからの社会の変化を考えるメディアです。加藤たけし&佐藤茜が夫婦2人で運営しています。